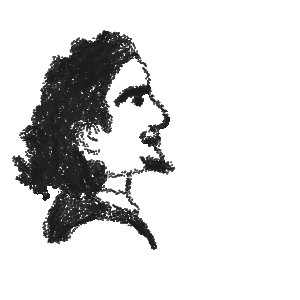地球上に残された"人類未踏の地"はあるけれど、
潜水艇も宇宙船も使わずカラダひとつで行けるのは地底だけ。
暗くて狭くて寒そうな地底への入口といえば洞窟だ。
国内外1000超の知られざる洞窟に潜ってきた洞窟探検家による、
逆説的サバイバル紀行"洞窟で遭難する方法、教えます"。

著者プロフィール
吉田勝次(よしだ かつじ)
1966年、大阪生まれ。国内外1000超の洞窟を探検・調査してきた日本を代表する洞窟探検家。(社)日本ケイビング連盟会長。洞窟のプロガイドとして、TV撮影のガイドサポート、学術探査、研究機関からのサンプリング依頼、各種レスキューなど幅広く活動。THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY(米国洞窟協会会員)。(有)勝建代表取締役。同社内の探検ガイド事業部「地球探検社」主宰。ほか探検チームJ.E.T (Japan Exploration Team) と洞窟探検プロガイドチーム「チャオ」の代表。個人ブログ「洞窟探検家・吉田勝次の足跡!」では日々の暮らしから最近の海外遠征まで吉田節で綴る(動画あり)。甘いものに目がない。

人類未踏地をゆく
世界洞窟探検紀行
第1話
怖がりの洞窟探検家
文と写真 吉田勝次(洞窟探検家)
◎洞窟で迷うと泣きそう
暗くて、狭くて、寒い洞窟に入っていくのはなぜ? とよく聞かれる。危険を犯してまでなぜ洞窟に潜るのかと。ほかに楽しいことはいっぱいあるよね? と疑問に思われるみたい。それから、よほど暗くて狭い場所が好きな変人に違いないと思われている節もある。ところが、ボクは高所恐怖症で閉所恐怖症。寒いのも苦手。水中も怖いし、洞窟で迷うと泣きそうになる。

◎はじめての探検
中学生の頃までは、街中のどこにでもある歩道橋でさえ立って歩いて渡れないほど。大人になって登山に初めて挑戦したときも、岩壁や氷の壁を登っているときは足がガクガク。
洞窟探検を始めてからも、洞窟の長く狭い空間を移動しているとき、急に恐怖心が襲ってきて前に進めなくなったこともあった。深い縦穴に降ろしたロープにぶら下がる瞬間、ロープが切れるんじゃないか? と不安になるのはいつものこと。洞窟の中にある、水路の狭い部分をくぐり抜けるときは恐怖心が倍増。動けなくなったらタンクの空気が残っているあいだしか生きられない! そんなことになったら大変だと考えてしまう。
たくさんの支洞が迷路のようになっている洞窟では時々、迷ってしまうときもある。そうなると緊張感と恐怖心で押しつぶされそうになる。脂汗が出てくるのが自分でもよくわかり、冷静になることだけに集中する。パニックになったら助かるものも助からないからだ。

真っ暗な洞窟の中で奥へ進む原動力は、自分が苦手なことに対してなにくそと思う性格と、少しの我慢強さかもしれない。それから、単純に前に進みたいという強い気持ちだろう。でも、前に進むことだけを優先してしまったら、戻れなくなる確率は高くなる。
好奇心と探究心は、前に進むための原動力にはなるけれど、それだけでは危険を察知して回避したり、戻る適切なタイミングを見誤ってしまう。もしボクがまったく洞窟を怖いと思わない人間だったとしたら、すでに生きていないかもしれない。
前に進むのは、好奇心や探究心が恐怖心に勝っているとき。逆に恐怖心が好奇心と探究心を超えたときは潔く戻るときだ。探検家は臆病なほど沈着冷静、用意周到なのだ。
それでも、20~30歳代の頃はいつも前進あるのみ。アクシンデントやハプニングに遭遇するうちに、恐怖心は増幅されていった。これまで3回ほど洞窟が怖くなり、一歩も前に進めなくなり、洞窟から足が遠のいた時期がある。でもまた時間を置くと行けるようになるから不思議だ。
山を登り、川を渡り、崖を登って洞窟にたどり着き、狭い通路を何日も這いずりまわって劣悪な空間を進むには、ある程度の強い肉体は必要。でも、肉体よりも気持ちのほうが大切。年齢を重ね、1000を超える国内外の洞窟に入ってきたこともあり、ようやく腹を据えて行動できるようになってきた。それでもやはり泣きたくなることはあるけれど、少しは強い気持ちを持てるようになった今日この頃である。

狭いドロドロの穴を通過したところ。
◎たくさん魚が捕りたくて
国の天然記念物で観光地として知られる秋芳洞、世界遺産のカールスバッド洞窟(アメリカ)、フォンニャ洞窟(ベトナム)、ワイトモ洞窟(ニュージーランド)などのいわゆる観光洞窟には一年中、大勢の人が訪れる。きっと人それぞれ、洞窟の何かに心が動かされたのだろう。
こうした観光洞窟のさらに奥や、観光化されていないどころか、いまだかつて誰も入ったことのない人類未踏の洞窟に潜るのが洞窟探検家だ。日本ではあまり馴染みのない洞窟探検だけれど、海外とくに欧米では「Caving ケイビング」というアウトドアスポーツのひとつとして人気があり、フランスはもっとも盛んな国として知られている。

日本で生まれて日本で育ったのに、なぜボクが洞窟探検家になったのか。そのきっかけは、思い返してみれば子供のころに遡る。
生きものが大好きで、自宅に100種類以上の動物を飼育。カブトムシ、ウサギ、リス、トカゲ、ヘビ、ワニ、ゾウガメ……。生きものを飼育するには知識が必要なので、一番の愛読書は生きもの図鑑。小学校の友達から「動物博士」と呼ばれていた。
飼育する生きものはなるべく自分で捕る主義で、毎日のように自宅近くの水路にフナや鯉、ナマズなどを捕りに行っていた。水路といっても、幅3メートルほど、水深30センチメートルぐらいの、いわゆるドブ川。工場や一般家庭からの排水も流れ込んでいるこのドブ川へ毎日行き、生きものを捕まえることに真剣に取り組んでいた。
水路にはフタのない明るい場所と、フタがあるために暗いところがあり、初めこそフタのない光の入るところで魚を獲っていた。ところが、少しずつフタのある真っ暗な場所へ、懐中電灯を持って入るようになった。怖くてたまらないので、少しずつしか奥へ進めない。フタのある水路の天井は低く、子供でも中腰で歩かないと進めないほどだった。
フタの上は自動車が走っていて、ほぼ50メートルおきに鉄の網状のフタになっているところだけ、太陽の光がスポットライトのように少しだけ射し込み、真っ暗な水路の中を照らしていた。真っ暗で不気味ではあるけれど、フタのある水路のほうに魚がたくさんいるので、魚を求めて少しずつ暗闇の奥へ入っていったのだった。
そのうちに何百メートルも水路の奥に行けるようになり、いつしか遠くに見える光が反対側の出口なのだと気づく。でも出口まではまだかなりの距離があり、恐怖心ですぐには行けそうもない。所々に深いところがあり、いきなり落ちてびっくりして逃げ帰るようなこともあった。それでも、また懲りずに真っ暗な水路の奥へ少しずつ進むことの繰り返し。毎日のように通い、少しずつ奥への距離を伸ばしていた。ドキドキワクワクと怖い怖いという相反する気持ちが入り交じる、誰もが子供のころに一度は体験したことがあるだろう。
水路の探検はある日、とうとう大きな国道を越えて向こう側に到達! フタのある水路は距離にして500メートルくらい。出口のある地区には、地上から行ったことはあったけれど、真っ暗な水路を歩いて辿り着いた出口から見た地上の景色はまったく違って見えた。そのときの大きな感動は生涯忘れられない。いま思えば、このときの経験が探検家としてのはじめの一歩であった。
また、子供の頃に放映されていたテレビ番組の探検モノ、冒険モノ、未確認生物モノをかじりついて観ていたので、探検へのあこがれは増幅された。少年時代を過ごした1970年代は「水曜スペシャル」の黄金時代。「ガンバの冒険」「宝島」「トムソーヤの冒険」といったアニメも放映されていた。
ところが、小学校を卒業したあとは、多くの人がそうであるように、生きものへの興味は徐々に薄れ、探検はおろか、自然と無縁の毎日を過ごして、あっという間に20歳になった。社会人になり、履歴書を出して面接を受けて就職出来たことがなく、他人の言うことを聞くのが嫌、何より独立心が強かったので21歳のときに建設業の会社を起業。仕事は順調、でも数年もすると仕事ばかりの毎日に物足りなさを感じるようになった。
スキューバダイビングと登山を始めたのは23歳になったころ。スキューバダイビングといっても、南の島のコバルトブルーに輝く海にグループで出掛けて行くようなことはなくて、一人で琵琶湖と長良川へ潜りに行った。登山は、ロッククライミングから冬山まで一年を通して山通い。こうしてまた自然の中で遊ぶようになったものの、どんなに潜っても、どんなに登っても、何か物足りなさが残る。それが何なのか? 当時のボクにはわからないまま。
その頃から、鍾乳洞があると必ず立ち寄るようになり、観光鍾乳洞によくある洞内をライトアップしたところよりも、「これ以上は立ち入り禁止」という看板の奥が気なるなと、少しずつ思うようになっていた。
◎真っ暗な洞窟に一筋の光
観光鍾乳洞ではない、自然の洞窟に入る機会に恵まれたのは28歳のとき。その洞窟は観光化されてないとはいえ、いま思えば潜るのは大変でなく、見所も少なかった。それでも、洞窟の暗闇の中を進みながら「これからやることはきっとこれだな! やっと見つかった!」と思えた。目の前は真っ暗なのに「頭の中がパッと明るくひらけた」のだ。
自然の洞窟は、大人一人がやっと通ることのできる狭い通路、垂直の縦穴、断崖絶壁は当たり前。わずかな空間が水に満たされ、地下河川や地底湖になることもよくある。これから当連載で詳しく紹介していくように、暗闇の中には実に変化に富んだ地形が待っている。入口からは想像できない世界が洞窟の奥に広がり、その景色は到達した者だけが見ることができる(でも大丈夫。きちんと写真を撮って皆さんにお見せします!)。

◎洞窟探検はやめられない
洞窟探検はスポーツ的な要素だけはなくて、学術的にも興味深いフィールドである。先人たちの住居だったり、現存しない生きもの化石が残っていたり、目の前の生きものがその洞窟だけの固有種だったり……。考古学、地質学、地理学、古生物学、生物学、水文学など多種多様な学問と密接な関係にあることも洞窟探検の魅力。
「洞窟はただ潜って帰ってくるだけではなく、何かしら発見がある」
携帯電話も無線もGPSも使えない太陽の光も届かない非日常の世界。「洞窟探検」の「探検」について調べてみると「日常とかけ離れた状況の中で、危険を覚悟しつつ、未知の地域へ赴いてそこを調べ、何かを探し出したり明らかにする行為のこと」とある。つまり、先が見えない、人類未踏の洞窟に潜ることが本当の意味の「洞窟探検」なのだ。
人類がまだ誰も行ったことのない未知の空間がまだ地球のどこかにある。未知の世界を一度でも自分で発見してしまうと探検はやめられない。気がつくと、この瞬間、この場所で生きていることに感動するから。自分の一生を費やしても調べきれない未知の世界が目の前に広がっていると実感する瞬間。人間が本来誰もが持っている“未知への探究心と好奇心”を増幅させるドキドキワクワクが洞窟にはある。洞窟は、探検家のあこがれ、「未知、未踏、探検、冒険、発見」に満ちているのだ。
いま、インターネットや小型衛星のお陰で、奥深いジャングルでさえ容易に空から見える時代になった。ほとんどの山は誰かが登り、地表に人類未踏地はないと言ってもいい。だとすれば、地球上に残された未踏の世界は深海か地底のどちらかしかない。
深海は潜水艦に乗らないと行けないので、人の力のみで進む探検家にとって残された唯一の未踏地は洞窟である。地球上のまだ誰も足を踏み入れたことのない世界を探検するなら、洞窟探検家になる以外に道はない。
*もっと「洞窟探検」を知りたい人に最適の本:
吉田勝次著『素晴らしき洞窟探検の世界 (ちくま新書) 』。 本書は当連載を大幅に加筆修正して、新たにイラストレーションを掲載して一冊にまとめたものです。

挿絵:黒沼真由美
対談:五十嵐ジャンヌ
吉田勝次著『洞窟探検家 CAVE EXPLORER』(風濤社)。話題の洞窟王が切り撮った、悠久の時と光がつくる神秘。大自然が生み出した総天然色の魔法! 大判写真集
【バックナンバー】
第1話 怖がりの洞窟探検家
第2話 すごい洞窟の見つけ方
第3話 ある遭難しかけた者の物語 その1
第4話 ある遭難しかけた者の物語 その2
第5話 三重県「霧穴」探検 その1
第6話 三重県「霧穴」探検 その2